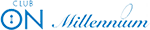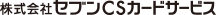斑紫銅酒器 Tanrei 黒仕上げ[ZD559]
美味しい日本酒が揃う新潟のお酒好きが作った冷酒専用の酒器。 手になじむ大きさと形、そして程よい持ち重りが魅力です。日本酒の繊細な味と香りをそのままに楽しんでいただけるよう、飲み口を絶妙な薄さに仕上げました。 内側は黒色の本漆仕上です。 ■新潟県無形文化財認定の伝統製法で、一つ一つ手作り 約600年前に新潟県柏崎市で鋳物業を開始し、1978年伝統的蝋型鋳造法が新潟県無形文化財の認定を受けました。 鉱物を溶かし、土で作った鋳型に流し込むと新たな役割を担って鋳物(いもの)が誕生します。 鋳物は古代には神器となり、中世には鐘や釜となり、現代では日々に寄り添う道具となって人の暮らしに溶け込んできました。 鉱物・土・炎という神からの預かりものから成り、大地の力を宿し、自然の環の一部として人の営みの傍で共に時を重ねます。 ここで生まれた鋳物が、人それぞれに積み重ねられてゆく時間の中で小さなあかりとなるよう、想いを込めて制作を続けて行きます。 <工房の沿革> 約600年前:新潟県柏崎市で鋳物業を開始。 江戸時代:由緒正しき鋳物師として朝廷より許状を受け釣り鐘や塩釜を制作。 江戸末期:原 得斎より技術を継承し蝋型鋳造法で美術工芸品を主力商品に据える。 1978年:伝統的蝋型鋳造法が新潟県無形文化財の認定を受ける。 1981年:皇太子殿下への献上品制作。 2010~12年:新潟県グローバルブランド『百年物語』参加。 2015年:日本伝統工芸新潟県最高賞受賞、以降入選。 翌年日本金工展受賞、以降入選。 東日本伝統工芸展入選、以降入選。 2016~18年:経済産業省 関東経済産業局とシンガポールデザイン庁の協調支援事業『KYO project』参画。 2017年:当代が五代晴雲を襲名する。 2018年:JR 東日本おみやげグランプリ銀賞受賞。
 大久保鋳物『五代晴雲 原惣右エ門工房』
大久保鋳物『五代晴雲 原惣右エ門工房』

古より柏崎に伝わる不思議な発色の銅鋳物
艶のある赤銅色の鋳肌に、赤紫色の斑紋(斑模様)が表れた独特の発色。これは銅鋳物の表面を焼いて斑紋をまとわせた「斑紫銅(はんしどう)」という銅器で、新潟県無形文化財である「大久保鋳物」の特徴とされています。
室町時代後期から江戸時代にかけ、柏崎では鋳物師たちの集落が形成され、大久保鋳物が生まれました。
現在もこの伝統を大久保で唯一受け継いでいるのが五代晴雲 原惣右エ門工房で、主に2つの鋳造方法で花器や酒器、茶道具、アクセサリーなどを製作しています。


【蝋型鋳造】
原型の蝋を土で覆い固め、炭火で焼いて蝋を溶かし出し、そこに銅の合金を鋳込む伝統的な手法で、最後には原型も鋳型も残らないため1点しか製作できません。
【生型鋳造】
砂を鋳型とする近代的な手法で、ある程度の量産が可能です。