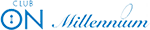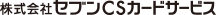ますの寿し 特撰 常温配送 【配送不可地域】 北海道、青森県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、長崎県、鹿児島県、大分県、沖縄県、離島
天然サクラマスを通常の1.5倍使った逸品。 天然羅臼(ラウス)昆布の出汁で炊き上げたコシヒカリに、まろやかな千鳥酢を合わせた酢飯が当店の自慢です。 ふるさと富山の誇りにかけて、オリジナルの風呂敷に包んでお届けします。 【製造】 (株)青山総本舗(富山県富山市新富町1-4-6) 【配送不可地域】 ・北海道、青森県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、長崎県、鹿児島県、大分県、沖縄県、離島への配送は承れませんので、ご了承ください。 事業者情報 事業者名/ますの寿し青山総本舗 連絡先/076-432-5324 営業時間/8:00 -16:00 定休日/日曜日・月曜日(月曜が祝日の場合は火曜日休) 【関連キーワード】 ますの寿し 富山 特撰 寿司 魚貝類 水産 食品 ギフト お取り寄せ 和食 伝統料理 おせち 期間限定 魚介類 食材 贈り物 国産 和風 惣菜
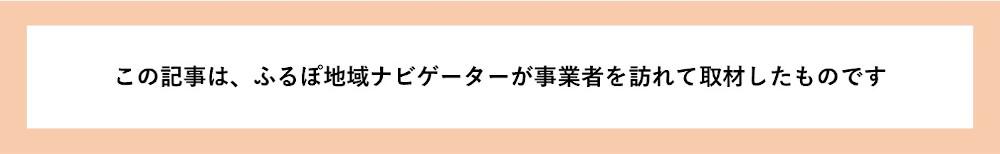
富山グルメといえば、ます寿司

駅弁としても人気が高い、富山名物「ます寿司」。富山市内には専門店が20軒以上あり、マスの身の厚さや酢飯の固さ、酸味の具合など、店ごとに個性を競っています。
これだけ多くの専門店があれば当然、地元の人それぞれにひいきの店があるはず。市内でおすすめの店を尋ねると、高確率で名前が挙がるのが「青山総本舗」。昭和22(1947)年創業の老舗です。
天然サクラマスを使った「ますの寿し特撰」

今回ご紹介するのは、青山総本舗の「ますの寿し特撰」。波と魚をデザインした風呂敷で包まれており、贈り物として求める人も多いそうです。

富山平野を流れる神通川(じんづうがわ)では、かつて多くのサクラマスが獲れましたが、環境の変化とともに数が減り、近年の漁獲量はごくわずか。そのため富山のます寿司は、養殖マスを使うのがスタンダードとなっています。そんななか、こちらの「ますの寿し特撰」は貴重な北海道産天然サクラマスを使用。身の厚さは、同店の定番商品の1.5倍という贅沢さです。
3代にわたって受け継いできた老舗の味

「これ、僕が作りたくて作っている商品なんですよ」。そう言って笑うのは、店主の青山益広(あおやま やすひろ)さん。作りたくて作っている。その言葉に興味を引かれ、詳しく話を聞きました。

青山総本舗の初代が営んでいたのは、神通川でとれる川魚を商う店。サクラマスをはじめ、コイやフナなど季節の川魚を扱い、それらを加工したかば焼きや干物なども店頭に並べていたそうです。そのひとつがます寿司でした。
3代目として伝統を守り継ぐ青山さんには、大切にしていることがあります。それは「こだわりではなく“理(ことわり)”にもとづいて、おいしさを追い求めること」。初代から脈々と続くます寿司作りですが、「製法にもおいしさにも必ず理由、すなわち“理”があるはず。理由もなく伝統にこだわることは、進化をやめてしまうことだと思うんです」と話します。
伝統の味を進化させる“理”とは?

“理”のひとつが素材。米は富山県井波地区の特別栽培米。収穫後、火力を使わない除湿乾燥で風味を保った米を使います。酢は全国30種類以上の銘柄を試し、京都の老舗の千鳥酢を選びました。笹は新潟県産のクマザサを取り寄せています。「新潟のものは色も香りも抜群。国産だからコストは高くつきますけど、お客さんに喜んでもらえるなら、それでいい」と青山さんはにっこり。
一つひとつの工程にどんな理由があるのかも、徹底的に研究したそうです。たとえば酢飯。「にぎり寿司の職人さんは、シャリを切ってうちわであおぎますよね。でも大阪寿司(押し寿司や巻き寿司)ならどうか。文献を読むと、酢を米の芯まで吸わせるために時間をかけてゆっくり冷ました方がいい、とある。うちわで風を送ってまで、冷ます理由はないんです」

25歳の時、同店に婿養子として入った青山さんは「なぜこの工程があるのだろう」「なぜこの素材を使うのだろう」と、「なぜ?」がいっぱいの毎日だったそう。「伝統だから、なんて理由にならない。理由が分かれば、もっといいものを作れるかもしれない。だから調べて、考えて、試して。その繰り返しですよね」
青山さんは“理”にもとづいて改良を加え、伝統の味をより高みへと引き上げてきました。その真骨頂が、返礼品の「ますの寿し特撰」というわけです。
毎朝5時から厨房に立ち、丁寧に手作り

特別に「ますの寿し特撰」を作っているところを、見学させてもらいました。こちらが天然サクラマス。立派な大きさですね!「これは体長50~60cm、3kgほどあります。このサイズはとても貴重なんですが、値段より質を優先して卸してもらってます」と青山さん。

この商品の特徴のひとつが、サクラマスの身の厚さ。おいしさを追求した青山さんがたどりついたのが、酢飯と身が2対1という割合でした。「他の商品より肉厚ですが、厚ければ良いというものでもないので、なかなかバランスが難しいんですよね」。天然サクラマスの風味や食感と、酢飯のおいしさの相乗効果をねらい、青山さんが見出した黄金比です。

曲げわっぱに笹を敷き、塩をした切り身を酢でしめて丁寧に並べます。酢でしめて時間をおくと身が固くなるため、酢じめをするのは作る直前。つややかな身が敷き詰められたところへ酢飯をのせ、ふたをして重しをします。
富山の食文化を後世へ伝えるために

重しをかけ終えた青山さんに「作りたくて作っている」という言葉の意味を尋ねてみました。するとこっそり教えてくれたのが「ますの寿し特撰」の原価。え?そんなにコストがかかっていたら採算が合いませんよね?!と驚く私に「そう、商売のことだけを考えたら、こんなに立派な天然サクラマスは使えません」と笑いながらうなずきます。
「でもね、作り続けることには意味があると思うんです」と青山さんは続けます。「富山のます寿司は古来、天然サクラマスを使っていました。今は素材が貴重ですから『ますの寿し特撰』は限られた数しか作ることができません。だから商売というよりも、本物を伝える使命っていうんですかね。富山の食文化を守ることが、いつか必ずこの店や地域のためになるはずだと思って、作り続けているんです」
素材の旨みが引き立て合う、極上のます寿司

取材を終え、いそいそと小風呂敷の包みを開くと、中には風情ある曲げわっぱ。笹のすがすがしい香りが漂います。丁寧に包丁で切り分けたら、もう待ちきれません!
美しい桜色をした一切れを口に運ぶと、天然サクラマスのしっとりと柔らかい食感にまず驚きます。厚切りにしたサクラマスの、優しくまろやかな旨み。きりっと酸味のきいた酢飯。素材それぞれの味わいがじんわりと口の中に広がり、思わず笑みがこぼれます。青山総本舗の、こだわりならぬ“理”を凝縮した「ますの寿し特撰」。富山の食文化の奥行きを、たっぷりと堪能させてくれる逸品です。

旨さを追求し、進化を続ける老舗の味わい
ます寿司のルーツは江戸時代にさかのぼります。ある富山藩士が神通川のサクラマス(一説ではアユ)で寿司を作り、将軍・徳川吉宗に献上したところ絶賛を受けたとか。以来約300年にわたり、富山に受け継がれてきた郷土料理です。
私自身、富山に行くと必ずます寿司を買い求めるファンのひとり。「ますの寿し特撰」の、食べ終えるのがもったいないほどの豊かな味わいには、すっかり魅了されました。そういえば青山さん、「まだまだ味わいが進化するかもしれません」と言っていましたよ。ます寿司ファンにとって、こんなにワクワクする言葉はありません!

中部支部(富山県富山市担当) / 森井 真規子(もりい まきこ)
石川県小松市在住のライター。航空自衛隊、海外生活を経て故郷にUターン。金沢のライター事務所で修業を積み、2005年からフリーランスで活動しています。出会う人やモノ、コトのストーリーを丁寧にすくいあげ、分かりやすい言葉で伝えることを心がけています。
路面電車が行き交う、風情豊かな富山のまち。路面電車に乗って、市内のます寿司店をめぐる旅もおすすめです。