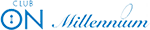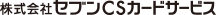郷土玩具「鯰押え」 鯰軕(なまずやま) 伝統工芸 郷土玩具 工芸品 お土産 ユネスコ無形文化遺産からくり人形 民芸品 伝統工芸品 手作り置物 木製 インテリア 縁起物 岐阜県 大垣市
「鯰押え」は、「大垣まつりの軕行事」(ユネスコ無形文化遺産登録)で曳き回される十三輌の軕の一つ「鯰軕」において、水上で踊る大鯰を老人が瓢箪を振りかざして押さえようとする「ろくろからくり人形」を型取った玩具です。 本玩具は江戸末期に幼君の遊び道具あるいは疱瘡除けの呪禁・地震避けのお守りとして制作されたとされ、その後形を変えながらも幾多の人によって継承され、現在は「鯰軕」を保有する魚屋町町民が一つ一つ手作りで制作し、今なお郷土玩具として親しまれています。 〈内容量・サイズ〉 サイズ:230mm×82mm×156mm(H) 〈製造地〉 岐阜県大垣市魚屋町 〈原材料〉 和紙・板紙・木材・石膏・水性塗料・塩ビ板 ほか 〈注意事項〉 内部のからくりは細い糸等で作られており、紐の操作は軽く優しくお願いします。
 生産者の声
生産者の声
当玩具は、「鯰軕」を保存・管理する魚屋町「鯰軕保存会」の有志により、お人形本体をはじめ台・ケースに至るまで全て手作りで制作されています。
また、例年5月の大垣祭りに八幡神社前で奉納する「鯰軕」のからくり芸を表現すべく、この玩具も翁人形の瓢箪と鯰が動く仕掛けとなっており、桶後方の紐を引くと、老人が持つ瓢箪が上下し大鯰が回転します。
一つ一つ手作りですので、顔の表情・着物の柄・からくりの動き等に個性があります。
手作りの良さをお楽しみいただきたいと思います。



 大垣まつりの紹介
大垣まつりの紹介

藩主からいただいた三両軕と10か町の軕がのこっており、さらに東のからくり芸と西のおどりというそれぞれの地方のお祭りの文化の特徴をもつことから、平成27年(2015)に国重要無形民俗文化財に指定されました。
そして、平成28年12月1日に「山・鉾・屋台行事」の1つとしてユネスコ無形文化遺産に登録されました。
 鯰軕(なまずやま)
鯰軕(なまずやま)


軕全体が名匠によって造られたと伝えられ、屋根は透かしの八角籠目細工による竹網張り、前後には雲に日・月を彫刻し、屋根の六本の柱は最も軽く作られ、前後左右に揺れる仕組みになっています。
からくり芸は「ろくろ」を使い、笛・鐘・太鼓の賑やかなお囃子に合わせ、水上で踊り狂う大鯰を、翁が金色の瓢箪を振りかざし全身を振るわせながら押さえようとする動作が何とも面白く、見る人を楽しませてくれます。
掲載内容について、調査日により古い情報の場合もあります。詳細は各自治体のホームページをご覧ください。また、万一、内容についての誤りおよび掲載内容に基づいて損害を被った場合も一切責任を負いかねます。