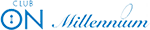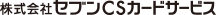猟師と鹿革サコッシュ作り体験 2名様|伊豆市 レザークラフト 狩猟 ハンドメイド ジビエ
伊豆市が大好きなスタッフと鹿革クラフトをしながら、伊豆の鹿問題や自然について考え、日々の暮らしを見つめなおすきっかけとなるプログラムです。 鹿革にポンチで穴を開けて、ひと針ひと針手縫いで丁寧に製作します。 鹿革クラフト作家のスタッフが丁寧に教えてくれるので初めての方でも安心です。 注目ワード 【静岡県 伊豆市 鹿革 レザークラフト 体験 針 手縫い 製作 クラフト 作家 初心者 財布 ミニ財布 小銭 カード ポシェット おでかけ レザー カシミヤ ランチ 伊豆市産 有機野菜 野菜 鹿肉 自然 考える チケット】 地場産品基準
- 容量
- 〇スケジュール ・集合場所:またね自然学校(またね村) 静岡県伊豆市八幡1041-2 ・集合時間:10:50 ・解散予定:16:00(※終了時間は前後する可能性があります) 〇注意点など ・昼食について:事前に済ませてからお越しいただくか、休憩中に簡単に食べられるものをお持ちください。 ・服装について:動きやすく、汚れてもよい服装でお越しください。 ・サコッシュの革の色について:在庫状況によって変わるのでお問い合わせください。 ・その他:ワークショップ中の写真撮影を行うことがあります。掲載NGの方は事前にお知らせください。

 鹿革の魅力
鹿革の魅力
鹿革の魅力は、しなやかで、軽く、手に吸い付くような滑らかさ。
もともと油分を多く含み、水に強く、ほとんどお手入れのいらない丈夫さです。
近年、鹿肉はジビエとして認知され、飲食店も増えてきています。
しかし、革として流通するのは、その中でもほんの数パーセント。
命の一部である皮は、多くの場合、活かされることなく処分されているのが現状です。
この革を無駄にせず、日々の道具として誰かの手に届けたいと私たちは考えています。
山の恵みと手づくりの温もりが、日常にそっと寄り添います。
そして鹿革は、じつは日本では昔から武具や装束に使われてきた、伝統的で馴染みのある素材でもあります。
自然と共に暮らしてきた日本人にとって、ごく身近で、知恵と工夫とともに生きてきた存在だったのです。
使い込むほどに手になじみ、色艶が深まり、まさに“育てる革”として長く楽しむことができます。

 手で紡ぐ命の物語
手で紡ぐ命の物語
日本各地で増えすぎた野生の鹿は、農作物や森林を荒らし、深刻な環境問題となっています。やむなく駆除された命を、ただ「害」として終わらせないために。
私たちはその命の恵みを、丁寧にいただき、ツノや革を新たな命のかたちへと変えています。
このサコッシュは、一つひとつ手縫いで仕立てる、あなただけのクラフト体験。
鹿のツノをワンポイントにあしらい、世界にひとつの存在感を放ちます。
自らの手で縫いあげることで、素材の物語はより身近になり、日々の暮らしに深みを与えてくれるはずです。
私たちが届けたいのは、ただの革小物ではありません。
そこには自然とのつながりや命の背景があり、「語れるモノづくり」があります。

 実施内容
実施内容
●鹿についての座学|なぜ「害獣」と呼ばれるのか?
野生動物としての鹿の生態や、農林業への被害、個体数増加の背景など、
「害獣」とされる理由を写真や現場の話を交えて学びます。
●猟師と一緒に森歩き|鹿の痕跡を探すフィールドワーク
実際に山へ入り、鹿の足跡、糞、食痕などを探しながら、
猟師の目線で自然を読み解くフィールドワークを行います。
動物の気配に耳を澄ませることで、見慣れた風景が少しずつ違って見えてきます。
●素材としての鹿革についての話|命を無駄にしないものづくり
軽くて丈夫、水にも強い「鹿革」は、古くから日本で愛用されてきた天然素材。
命をいただいたあと、その革をどう生かすか──猟師であり革職人でもある講師が、
鹿革の特徴や活用の背景をお話しします。
●鹿革クラフト体験|世界にひとつのサコッシュづくり
鹿革を使って、サコッシュを手作りします。
使う革は、一頭ごとに違う色や風合いを持つ天然素材。
裁断から縫製まで手を動かしながら、命のぬくもりを形にしていきます。
 またね自然学校
またね自然学校
『インタープリテーション』という手法を用いて、持続可能な社会を目指し環境教育に取り組んでいます。 インタープリテーションとは、自然・文化・歴史についての知識そのものを伝えるだけでなく、その裏側にある見えにくい「メッセージ」を分かり易く伝える行為のことです。 例えば、トレッキングであれば植物の名前を伝えるだけでなく、なぜその植物はその名前になったのか、なぜその場所に生息するのか、他の生命体とどのように関わり合っているのかというような視点から日本の昔の暮らし方や地球全体のことを考えてみたり、 狩猟体験であれば体験を通して命をいただくこと、「いただきます」の意味を改めて考えてみたり、インタープリターの感性と共に、広い視野で物事を考えるきっかけづくりをしています。