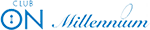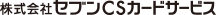【ご予約】日本産 羊の糸 約100g×1かせ ※2025年10月頃から順次配送 / 毛糸 手芸 編み物 羊 ひつじ 糸 和歌山 本宮 【tsg001】
国内で破棄されている羊毛を、 環境に配慮した洗い方で洗毛し、 糸にしています。 1かせにつき、約100gとなっています。 (ニット帽サイズを編むことができます。)
 日本産 羊の糸
日本産 羊の糸
国内で破棄されている羊毛を、環境に配慮した洗い方で洗毛し、
糸にしています。
1かせにつき、約100gとなっています。
(ニット帽サイズを編むことができます。)

■国産羊毛への想いと現状
国内で飼われている羊の数の統計を見てみると、以下の通り激減しています。
・1957年 約944,940頭
・2017年 約17,821頭
(出典元:公益社団法人畜産技術協会)
国内の羊の頭数が激減した理由はさまざまありますが、そのひとつの大きな理由として、洗毛工場の激減が挙げられます。
現在、国内では公害問題・環境保護の観点で洗毛工場はすべて閉鎖されました。洗毛できないということは、紡績工場や織物工場、ニット工場などの次の工程に進めず、国産羊毛の利用は進みません。そのため、現在国内の羊の毛の大半が未利用のままとなっています。
『日本で育った羊の毛を活用したい理由は、大きく2つ。』
①環境問題を他人事ではないと思えるのではないかということ
例えば、自分の畑で野菜を育てると、社会で起きている大きな問題(水や土の汚染、種、農薬など)を直接理解し、どうしたら良いのか考え行動できるのではないかと思います。織物や編み物が糸からできていて、その素材が近くのものであるということで、環境のことや、食べるもの着るもの住むところについて身近に感じられるのではないかと思います。
②安心を感じられること
自分の畑の野菜が安心でおいしいように、誰が育ててどんなところで育った素材なのかが分かると人は深く安心感を得られるはずです。安心は多くの人が望んでいることではないでしょうか。お金や物で安心を得るよりも絶対的な安心感をみんなが持てたら、世の中は平和だと思います。

■羊毛を洗う(洗毛)工程の廃液と手間
そこで問題となるのは、羊毛を洗う(洗毛)工程の廃液と手間です。
羊は衛生面で、1年に1~2回、人の手で毛を刈る必要があります。草を食み土の上で暮らす羊は、汚れや害虫から皮膚を守るためにラノリンという脂を出し、一年分の汚れをはじきます。衣や暮らしの中で羊毛を活用するには、この汚れと脂を洗い流す必要があります。匂いがでること、不衛生であること、脂があると紡ぎにくいし染まりにくいためです。

我が家で飼っている羊の毛は、お湯で洗っています。私たちが暮らしているところは山と川が近くにあり、自然がとても身近にあります。暮らし以上の廃液は出したくない、という想いでお湯洗い、または少しの石鹸水で洗います。

■私たちについて
和歌山県田辺市本宮町に移住して10年目になりました。5人の子どもに恵まれ、自然豊かな里山で暮らしています。子どもと動物たちがのびのびと健やかに育っている大自然にいつも感謝しています。
15年ほど前に「糸紡ぎ」に出会い感動し、紡いだ糸で編み物や織り物を制作し販売しています。
5年前から羊を飼い始め、わが家で育った羊の毛から作品をつくるようになり、その後、手仕事に興味のある方を対象に、羊の毛からものづくりをするワークショップ、編物や織物、フェルトなどをみんなでつくる会を開催するようになりました。
この頃から、以下のような思いを込めて、「くまの手仕事研究所」という屋号で活動を始めました。今では手仕事というテーマで繋がり合って仲間たちが増えていっています。
羊毛以外にも、綿、くず、ガマ、苧麻、まこも、アカメガシワ、藁などの素材でものづくりをしています。自然素材を使ってものづくりをする利点は、それぞれの素材の季節があり、その時その場所に生えて伸びてくるという凄まじい生命力にあやかれるというところです。
そして、なるべく素材の邪魔をすることなく、日々寄り添えるものをつくっていきます。その過程で手のひらを使い頭を休めることができます。みんなで集まり話しながら手仕事することで、胸がふわふわしてきて、身体とこころが整っていき、自分の生命力を感じることができます。

■羊飼いのはじまり
糸を紡いでいくうちに、素材の背景が気になるようになってきました。食材もなるべく近くのものが安心だなと思っていたので、もの作りの素材も自然と国産の物へと移行していきました。
ある日家族で愛知牧場へ遊びに行ったときに、羊の飼育員さん(丸岡圭一さん)とお話をしていて、羊毛を紡いでものづくりをしています、と話していると『羊を飼ってみたら?』と言われ、いつの間にか3頭の羊を飼っているという今に至ります。
丸岡さんとの出会いがなかったら、羊を迎えることはできなかったと思います。今でも羊飼いのプロとしてたくさんのアドバイスをいただいています。丸岡さん自身も国産羊毛の普及に全力を注いでいて、とても心強い先輩です。