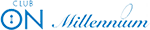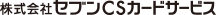越中陶の里 陶農館 オリジナルブランド 片口 化粧箱付 器 酒器 ドレッシング入れ 花器 伝統工芸 越中瀬戸焼 工芸品 陶器 ギフト 贈り物 F6T-031
富山県立山町にある越中陶の里「陶農館(とうのうかん)」は、伝統工芸「越中瀬戸焼」の産地にあります。当館では、現在活動されている窯元の作品の展示販売や、地元の粘土を使った陶芸体験などがあります。こちらの商品は、地元「越中瀬戸」の土を利用し、陶農館のスタッフが制作しているオリジナル商品になります。粘土から手作りのため、土の色や表情、釉薬の流れなど一つひとつ違う趣をお愉しみください。片口は越中瀬戸焼の窯元「庄楽窯」釋永由紀夫氏に原型のデザインを依頼し、陶農館で成形したものになります。酒器や、ドレッシング入れ、花器などにも使えます。 ※画像はイメージです。 ※割れ物です。お取り扱いにご注意ください。 ※1つ1つ手作りのため大きさ、色味が多少異なります。 事業者:越中陶の里 陶農館
-
越中瀬戸焼 ゆらゆら鉢 器 山田智子 1点もの 食器 うつわ 鉢 陶器 ギフト ...


立山の麓にある越中瀬戸焼は、430年以上の歴史ある伝統工芸品です。\\nわたしはこの土地で生活している中で見てきた景色、感じたものを作品に…という思いで作っています。\\nこの作品は、この土地の粘土で作り、薪の窯で焼成しています。\\n釉薬の白の結晶が、いろいろ景色を見せてくれます。\\n\\n<ご注意>\\n・それぞれ色の出方に個体差があり、画像の写真と異なる場合があります。\\n・寄附者様が見ていらっしゃる画面の色味と実物が異なる場合がございます。\\n\\n●越中瀬戸焼とは?\\n越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。\\n桃山時代、加賀藩2代目藩主・前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。\\nしかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。\\nその後、昭和時代に入り地元有志の発意によって瀬戸焼保存会を設立し、陶器製産を復活させました。\\n現在は、7人の作家が作陶を続けています。\\n\\n●越中陶の里 陶農館とは?\\n陶農館は、430年以上の歴史をもつ越中瀬戸焼の文化を伝えることを目的とした施設です。\\nここでは、現在の窯元の作品の展示・販売をしています。\\n返礼品を通して、多くの方に越中瀬戸焼のことを知っていただき、立山町に訪れてほしいという思いから出品しました。\\nまた、当館では越中瀬戸の粘土で陶芸体験をおこなっており、スタッフがわかりやすく指導いたします。
容量:■内容量\\n1個(縦7.5㎝×横7.5㎝×高さ8.5㎝)\\n\\n■原材料名\\n陶器
申込:通年
配送:決済確認から1~2ヶ月程度 ※年末年始など申込が集中した場合は、プラス1~2ヶ月お待たせすることがございます。
越中瀬戸焼 ビール杯 模様A 枯芒ノ窯 北村風巳 タンブラー コップ 食器 伝...


立山の陶土を使い、蹴ろくろと手びねりで作成しました。\\n薄く全体に泥釉を掛け、その上に貝を燃やした灰と薪窯で焼成した灰を合わせた釉薬を掛け、自作の薪窯で焼成。\\n炭素を含ませる事によって古陶のような風合いを出しています。\\n\\n●越中瀬戸焼とは?\\n越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。\\n桃山時代、加賀藩2代目藩主・前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。\\nしかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。\\nその後、昭和時代に入り地元有志の発意によって瀬戸焼保存会を設立し、陶器製産を復活させました。\\n現在は、6つの窯元が作陶を続けています。\\n\\n●越中陶の里 陶農館とは?\\n陶農館は、430年以上の歴史をもつ越中瀬戸焼の文化を伝えることを目的とした施設です。\\nここでは、現在の窯元の作品の展示・販売をしています。\\n返礼品を通して、多くの方に越中瀬戸焼のことを知っていただき、立山町に訪れてほしいという思いから出品しました。\\nまた、当館では越中瀬戸の粘土で陶芸体験をおこなっており、スタッフがわかりやすく指導いたします。
容量:■内容量\\nサイズ:縦9cm×横9cm×高さ12cm\\n重量:286g \\n\\n■原材料名\\n陶器
配送:決済確認から1~2ヶ月程度 ※寄附申込がお盆・連休前後の場合や寄附申込が集中した場合は、お届けまでお待たせすることがございます。
越中瀬戸焼 ビール杯 模様B 枯芒ノ窯 北村風巳 タンブラー コップ 食器 伝...


立山の陶土を使い、蹴ろくろと手びねりで作成しました。\\n薄く全体に泥釉を掛け、その上に貝を燃やした灰と薪窯で焼成した灰を合わせた釉薬を掛け、自作の薪窯で焼成。\\n炭素を含ませる事によって古陶のような風合いを出しています。\\n\\n●越中瀬戸焼とは?\\n越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。\\n桃山時代、加賀藩2代目藩主・前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。\\nしかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。\\nその後、昭和時代に入り地元有志の発意によって瀬戸焼保存会を設立し、陶器製産を復活させました。\\n現在は、6つの窯元が作陶を続けています。\\n\\n●越中陶の里 陶農館とは?\\n陶農館は、430年以上の歴史をもつ越中瀬戸焼の文化を伝えることを目的とした施設です。\\nここでは、現在の窯元の作品の展示・販売をしています。\\n返礼品を通して、多くの方に越中瀬戸焼のことを知っていただき、立山町に訪れてほしいという思いから出品しました。\\nまた、当館では越中瀬戸の粘土で陶芸体験をおこなっており、スタッフがわかりやすく指導いたします。
容量:■内容量\\nサイズ:縦9.0cm×横9.0cm×高さ11.5cm\\n重量:286g\\n\\n■原材料名\\n陶器
配送:決済確認から1~2ヶ月程度 ※寄附申込がお盆・連休前後の場合や寄附申込が集中した場合は、お届けまでお待たせすることがございます。
越中瀬戸焼 ビール杯 模様C 枯芒ノ窯 北村風巳 タンブラー コップ 食器 伝...


立山の陶土を使い、蹴ろくろと手びねりで作成しました。\\n薄く全体に泥釉を掛け、その上に貝を燃やした灰と薪窯で焼成した灰を合わせた釉薬を掛け、自作の薪窯で焼成。\\n炭素を含ませる事によって古陶のような風合いを出しています。\\n\\n●越中瀬戸焼とは?\\n越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。\\n桃山時代、加賀藩2代目藩主・前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。\\nしかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。\\nその後、昭和時代に入り地元有志の発意によって瀬戸焼保存会を設立し、陶器製産を復活させました。\\n現在は、6つの窯元が作陶を続けています。\\n\\n●越中陶の里 陶農館とは?\\n陶農館は、430年以上の歴史をもつ越中瀬戸焼の文化を伝えることを目的とした施設です。\\nここでは、現在の窯元の作品の展示・販売をしています。\\n返礼品を通して、多くの方に越中瀬戸焼のことを知っていただき、立山町に訪れてほしいという思いから出品しました。\\nまた、当館では越中瀬戸の粘土で陶芸体験をおこなっており、スタッフがわかりやすく指導いたします。
容量:■内容量\\nサイズ:縦9.0cm×横9.0cm×高さ11.5cm\\n重量:286g\\n\\n■原材料名\\n陶器
配送:決済確認から1~2ヶ月程度 ※寄附申込がお盆・連休前後の場合や寄附申込が集中した場合は、お届けまでお待たせすることがございます。
越中瀬戸焼 切立湯呑 2客組 (白と黒) 山田智子 1点もの 湯呑 ペア セット ...

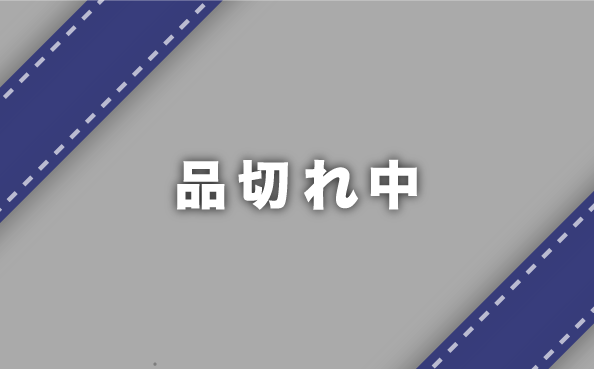

立山の麓にある越中瀬戸焼は、430年以上の歴史ある伝統工芸品です。\\nわたしはこの土地で見てきた景色、感じたものを作品に…と思い作っています。\\nこの作品は、この土地の粘土で作り、薪の窯で焼成しています。\\n少し小ぶりで、ちょっとしたときに使いやすいサイズになっています。\\n\\n<ご注意>\\n・それぞれ色の出方に個体差があり、画像の写真と異なる場合があります。\\n・寄附者様が見ていらっしゃる画面の色味と実物が異なる場合がございます。\\n\\n●越中瀬戸焼とは?\\n越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。\\n桃山時代、加賀藩2代目藩主・前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。\\nしかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。\\nその後、昭和時代に入り地元有志の発意によって瀬戸焼保存会を設立し、陶器製産を復活させました。\\n現在は、7人の作家が作陶を続けています。\\n\\n●越中陶の里 陶農館とは?\\n陶農館は、430年以上の歴史をもつ越中瀬戸焼の文化を伝えることを目的とした施設です。\\nここでは、現在の窯元の作品の展示・販売をしています。\\n返礼品を通して、多くの方に越中瀬戸焼のことを知っていただき、立山町に訪れてほしいという思いから出品しました。\\nまた、当館では越中瀬戸の粘土で陶芸体験をおこなっており、スタッフがわかりやすく指導いたします。
容量:■内容量\\n・白 1客(縦7.5㎝×横7.5㎝×高さ8.5㎝)\\n・黒 1客(縦7.5㎝×横7.5㎝×高さ8.5㎝)\\n計2客\\n\\n■原材料名\\n陶器
申込:通年
配送:決済確認から1~2ヶ月程度 ※年末年始など申込が集中した場合は、プラス1~2ヶ月お待たせすることがございます。
越中瀬戸焼 藁掛フリーカップ 四郎八窯 加藤聡明 カップ コップ フリーカ...


越中瀬戸の土を使用し、自作の薪窯「いってこい窯」で焼き上げました。\\n藁を原料にした釉薬を使用しています。\\n釉薬の流れ方は窯の場所や温度、掛具合によって変わります。\\n手になじむ、ふくらみのある形です。\\n\\n●越中瀬戸焼とは?\\n越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。\\n桃山時代、加賀藩2代目藩主・前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。\\nしかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。\\nその後、昭和時代に入り地元有志の発意によって瀬戸焼保存会を設立し、陶器製産を復活させました。\\n現在は、6つの窯元が作陶を続けています。\\n\\n●越中陶の里 陶農館とは?\\n陶農館は、430年以上の歴史をもつ越中瀬戸焼の文化を伝えることを目的とした施設です。\\nここでは、現在の窯元の作品の展示・販売をしています。\\n返礼品を通して、多くの方に越中瀬戸焼のことを知っていただき、立山町に訪れてほしいという思いから出品しました。\\nまた、当館では越中瀬戸の粘土で陶芸体験をおこなっており、スタッフがわかりやすく指導いたします。
容量:■内容量\\nサイズ:縦9cm×横9cm×高さ12cm\\n重量:260g\\n\\n■原材料名\\n陶器\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n
配送:決済確認から1~2ヶ月程度 ※お盆や連休前後は、通常よりもお時間を頂く場合がございます。 ※寄附申込が集中した場合は、お届けまで2~3ヶ月お待たせすることがございます。
越中瀬戸焼 貝灰釉山盃 枯芒ノ窯 北村風巳 酒器 盃 伝統工芸 工芸品 ギフ...


立山の陶土を使い蹴ろくろで作成しました。\\n蹴りろくろは、電動ろくろと比べて整った形になりすぎず、作り手の味わいが出ます。\\n薄く全体に泥釉を掛け、その上に貝を燃やした灰と薪窯で焼成した灰を合わせた釉薬を掛け、自作の薪窯で焼成しました。\\n炭素を含ませる事によって古陶のような風合を出しています。\\n\\n●越中瀬戸焼とは?\\n越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。\\n桃山時代、加賀藩2代目藩主・前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。\\nしかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。\\nその後、昭和時代に入り地元有志の発意によって瀬戸焼保存会を設立し、陶器製産を復活させました。\\n現在は、6つの窯元が作陶を続けています。\\n\\n●越中陶の里 陶農館とは?\\n陶農館は、430年以上の歴史をもつ越中瀬戸焼の文化を伝えることを目的とした施設です。\\nここでは、現在の窯元の作品の展示・販売をしています。\\n返礼品を通して、多くの方に越中瀬戸焼のことを知っていただき、立山町に訪れてほしいという思いから出品しました。\\nまた、当館では越中瀬戸の粘土で陶芸体験をおこなっており、スタッフがわかりやすく指導いたします。
容量:■内容量\\nサイズ:縦7.3cm×横7.3cm×高さ4.7cm\\n重量:89g\\n\\n■原材料名\\n陶器
配送:決済確認から1~2ヶ月程度 ※寄附申込がお盆・連休前後の場合や寄附申込が集中した場合は、お届けまでお待たせすることがございます。
越中瀬戸焼 黒釉筒茶碗 枯芒ノ窯 北村風巳 黒 茶碗 茶道具 茶器 伝統工芸 ...

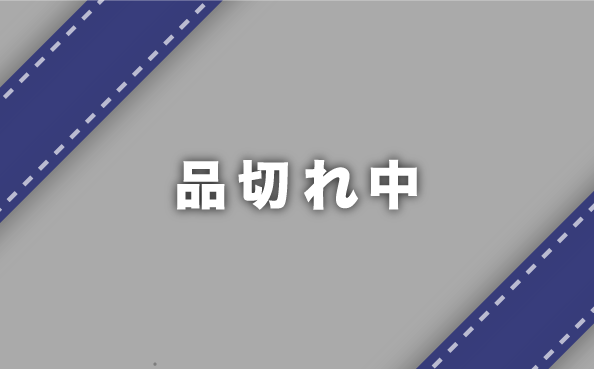

立山の陶土を使い、蹴ろくろで作成しました。\\n蹴りろくろは、電動ろくろと比べて整った形になりすぎず、作り手の味わいが出ます。\\n自作の黒釉を掛け、自作の薪窯で焼成することで、薪による灰もかかり雰囲気が出ました。\\n\\n●越中瀬戸焼とは?\\n越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。\\n桃山時代、加賀藩2代目藩主・前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。\\nしかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。\\nその後、昭和時代に入り地元有志の発意によって瀬戸焼保存会を設立し、陶器製産を復活させました。\\n現在は、6つの窯元が作陶を続けています。\\n\\n●越中陶の里 陶農館とは?\\n陶農館は、430年以上の歴史をもつ越中瀬戸焼の文化を伝えることを目的とした施設です。\\nここでは、現在の窯元の作品の展示・販売をしています。\\n返礼品を通して、多くの方に越中瀬戸焼のことを知っていただき、立山町に訪れてほしいという思いから出品しました。\\nまた、当館では越中瀬戸の粘土で陶芸体験をおこなっており、スタッフがわかりやすく指導いたします。
容量:■内容量\\nサイズ:口径9.0cm×高さ9.0cm\\n重量:213g\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n■原材料名\\n陶器
配送:決済確認から1~2ヶ月程度 ※寄附申込がお盆・連休前後の場合や寄附申込が集中した場合は、お届けまでお待たせすることがございます。
越中陶の里 陶農館 オリジナルブランド 湯呑と箸置 2個セット (白と黒) 化...


富山県立山町にある越中陶の里「陶農館(とうのうかん)」は、伝統工芸「越中瀬戸焼」の産地にあります。当館では、現在活動されている窯元の作品の展示販売や、地元の粘土を使った陶芸体験などがあります。こちらの商品は、地元「越中瀬戸」の土を利用し、陶農館のスタッフが制作しているオリジナル商品になります。粘土から手作りのため、土の色や表情、釉薬の流れなど一つひとつ違う趣をお愉しみください。お湯呑は小振りの大きさになり、ワインなどの酒器としても愉しめます。箸置は、筆置きなど多様に活用できます。\\n\\n※画像はイメージです。\\n※割れ物です。お取り扱いにご注意ください。\\n※1つ1つ手作りのため大きさ、色味が多少異なります。\\n\\n事業者:越中陶の里 陶農館
容量:陶器 湯呑と箸置2個セット(白と黒)\\n湯呑 縦6.3×横6.3×高さ8.0(cm)\\n箸置 縦5.5×横2.0×高さ2.0(cm)\\n(化粧箱付)