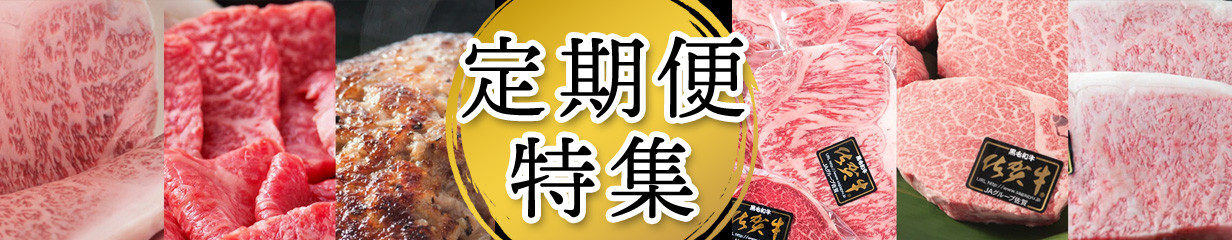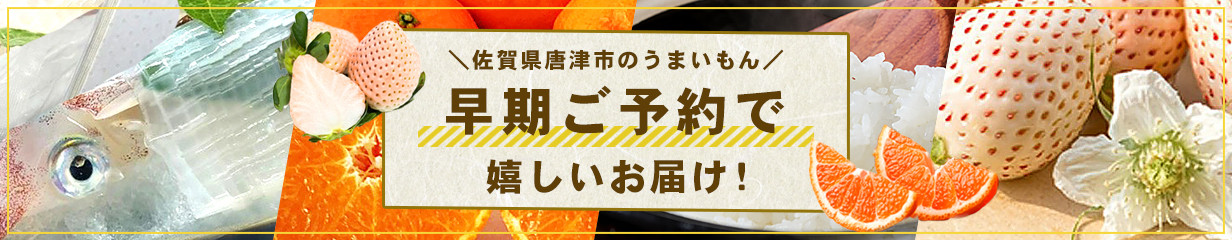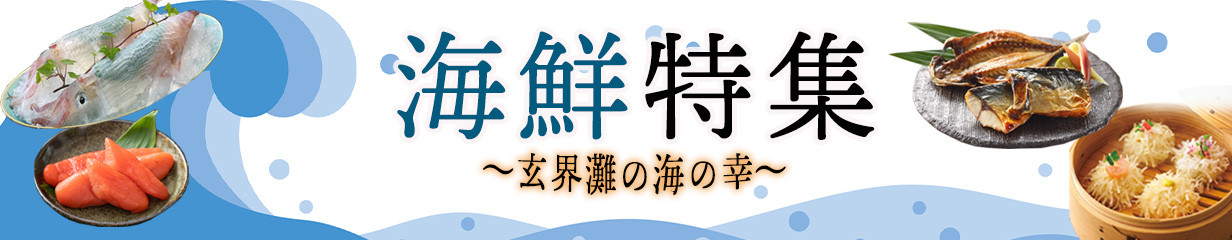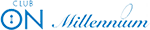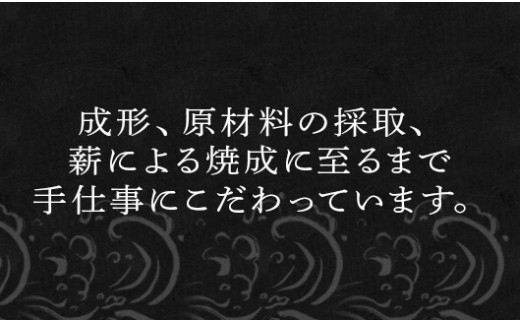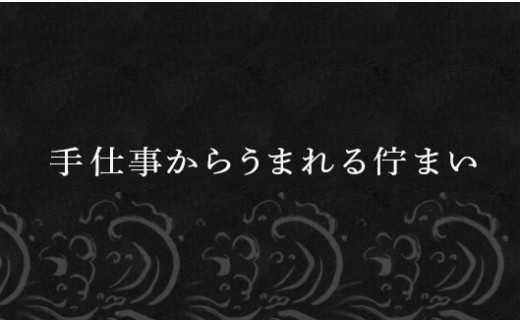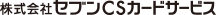【鏡山窯】粉引唐津片口酒器揃(井上公之作) 「2023年 令和5年」
手仕事からうまれる佇まい。薪窯から生まれる唯一無二の景色。唐津焼窯元・鏡山窯(きょうざんがま)当主井上公之(こうじ)作 片口と盃のセットです。 唐津焼窯元・鏡山窯は1969年、先代井上東也(とうや)が開窯。以来、成形はもちろん原材料の採取、薪による焼成に至るまでに手仕事にこだわっています。当主の井上公之は茶陶の伝統を引き継ぎつつ、生活に寄り添う器まで作品は多岐にわたります。こちらの作品は公之作 粉引唐津窯変片口と粉引唐津盃の酒器揃です。専用桐箱でお届けします。(サイズ粉引唐津片口 外寸12cm×17.2cm×高さ8.3cm 粉引唐津盃 外寸9.3cm×高さ3.3cm)写真現品を発送いたします。 唐津焼は土目が粗いため、釉薬の表面に貫入(細かいひび)が存在します。この貫入に水分などがしみ込み表情を変えていき、唯一無二の味わい深い作品に成長していきます。陶器は割れやすく欠けやすいので、取扱いには注意してください。 「唐津焼」の地域団体商標を登録や、国の伝統的工芸品の指定を受けている唐津焼協同組合です。現在18の窯元が加盟しており、直営の唐津焼総合展示場では、作風の変わった18の窯元の作品を一堂に会し、展示販売を行っています。伝統技術を継承しつつ、革新の技に取り組み、新しい作品が次々と生まれています。これまでとは違った唐津焼に触れてみませんか。
- 容量
 この商品を見ている人はこちらもチェック!
この商品を見ている人はこちらもチェック!
-
【岸岳窯三帰庵】朝鮮唐津耳付花入れ(冨永祐司作)

唐津焼発祥の地「北波多」で焼き上げた唐津焼を代表する朝鮮唐津花入れです。\\n\\n唐津焼の代表的な釉薬、朝鮮唐津を施した「朝鮮唐津耳付花入」です。花を活けて花器としても、鑑賞用としてもお使いいただけます。\\n(実寸サイズ直径14cm高19.6cm 木箱入り 写真現品を発送) 岸岳窯三帰庵 作\\n\\n唐津焼は土目が粗いため、釉薬の表面に貫入(細かいひび)が存在します。この貫入に水分などがしみ込み表情を変えていき、\\n唯一無二の味わい深い作品に成長していきます。陶器は割れやすく欠けやすいので、取扱いには注意してください。\\n\\n「唐津焼」の地域団体商標を登録や、国の伝統的工芸品の指定を受けている唐津焼協同組合です。現在18の窯元が加盟しており、\\n直営の唐津焼総合展示場では、作風の変わった18の窯元の作品を一堂に会し、展示販売を行っています。\\n伝統技術を継承しつつ、革新の技に取り組み、新しい作品が次々と生まれています。これまでとは違った唐津焼に触れてみませんか。
配送:入金確認より2週間以内に発送いたします
唐津焼 白唐津 彫絵 杯 三代中野霓林作 「2023年 令和5年」
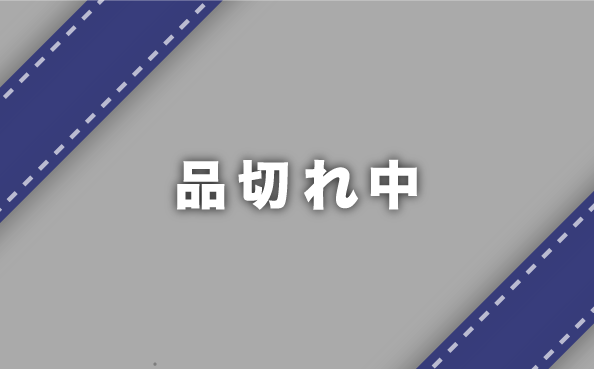

無心から生まれる炎の芸術 極致の美を求めて\\n\\n土から芽吹いたばかりの春の柔らかな草を思わせる模様が彫り込まれた、白唐津の杯です。\\nたっぷり掛かった白釉が、彫り込まれた草の模様に入り込み、やさしい雰囲気を醸し出しています。\\nまた、陶土に含まれた鉄分が黒い点となって白の釉薬の間から顔を出し、景色となっています。\\nお湯割りや氷を浮かべた焼酎はもとより、たっぷりとカフェオレを入れて一息ついたり、\\n深向付のように料理を盛ったり、茶碗蒸しを作ったり…\\nあるいは小さな剣山を入れてを生けたりと、使い方が広がる素敵な杯です。\\n\\n【中野窯 三代 霓林】\\n安政年間、初代松島弥五郎没後、\\n門下であった中野霓林(なかのげいりん)が窯を引き継ぎました。\\n霓林の功績により藩窯としての認可を小笠原長生公より受け、\\n小笠原家の家紋である『三階菱』を窯印として使用するようになりました。\\n徳川末期及び明治維新と共に、廃藩置県の為藩の加護なく中絶期に直面した際、\\nお茶碗窯として炎を絶やすことなく、今日の唐津焼隆盛の基礎をなしえました。\\n種田山頭火が初代に与えた「霓林」という雅号。霓は虹の意で、\\n「虹の林」という名前は唐津市にある虹の松原を思わせます。\\n現在は、平成26年に祖父からその名前を受け継ぎ、\\n三代中野霓林を襲名した中野正道が、唐津焼の伝統を踏まえ茶陶をはじめ、\\n細工物を手掛けています。
容量:唐津焼 白唐津 彫絵 杯 \\n三代中野霓林作 1個\\n・径:約10cm \\n・高さ:約8cm
申込:通年
配送:入金確認より1か月以内に発送いたします
唐津焼 粉引唐津 片口 三代中野霓林作
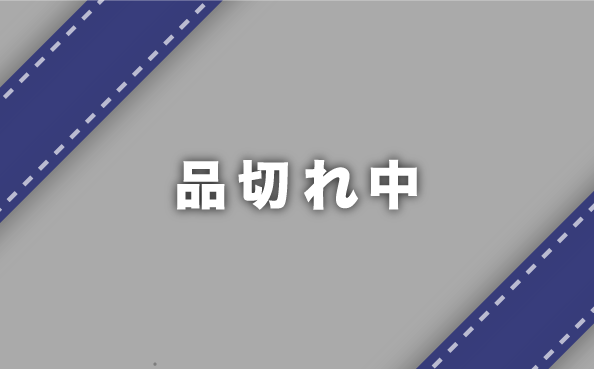

無心から生まれる炎の芸術 極致の美を求めて\\n\\n口辺部の片側に注ぎ口がついた片口(かたくち)の器です。\\nすぼめた口のような形が愛らしく心惹かれます。\\n少し楕円形のフォルムのこの作品は、器の内外に控えめな\\n梅花皮(かいらぎ)模様を見ることができます。\\n側面にはうっすらとした桃色の紅葉手という窯変が出てきており、\\n使い込んでいくうちに美しく変化していく過程を楽しむことができる器でもあります。\\nお酒を入れるものというイメージがありますが、湯冷ましとして使ったり、\\nお料理を盛り付けたり、花を生けたりすることもできる便利な器です。\\n湯切れ良く後引きしないように口作りも工夫されています。\\n\\n【事業者の思い】\\n安政年間、初代松島弥五郎没後、\\n門下であった中野霓林(なかのげいりん)が窯を引き継ぎました。\\n霓林の功績により藩窯としての認可を小笠原長生公より受け、\\n小笠原家の家紋である『三階菱』を窯印として使用するようになりました。\\n徳川末期及び明治維新と共に、廃藩置県の為藩の加護なく中絶期に直面した際、\\nお茶碗窯として炎を絶やすことなく、今日の唐津焼隆盛の基礎をなしえました。\\n種田山頭火が初代に与えた「霓林」という雅号。霓は虹の意で、\\n「虹の林」という名前は唐津市にある虹の松原を思わせます。\\n現在は、平成26年に祖父からその名前を受け継ぎ、\\n三代中野霓林を襲名した中野正道が、\\n唐津焼の伝統を踏まえ茶陶をはじめ、細工物を手掛けています。
容量:唐津焼 粉引唐津 片口 \\n三代中野霓林作1個\\n・長径:約15cm \\n・短径:約12cm \\n・高さ:約8cm \\n・容量約1合半(300cc)\\n
申込:通年
配送:入金確認より1ヶ月以内に発送いたします。 返礼品の発送時には出荷お知らせメールをお送りしております。
 唐津☆おススメ返礼品特集
唐津☆おススメ返礼品特集