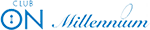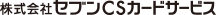G181p 〈平戸窯悦山〉菊尽しボンボン入れ
長寿を願う菊花を華やかに蓋に配置した白磁の蓋物です。菊花は伝統技法の菊細工といわれる捻り細工のひとつの技法にて制作、親指先ほどの塊から竹べらを用い、花弁を一枚一枚起こして菊花を彫っていきます。キャンディーボックスや大切なものを入れるための器です。 [三川内焼・みかわち焼・うつわ・器・セット・ペア・作家・伝統工芸・肥前・日本遺産] ~五感で感じる日本磁器のふるさと~日本遺産・肥前やきもの圏について 古くから焼き物の産地として栄えた肥前地区(佐賀県、長崎県)。 有名な有田焼や波佐見焼のほかにも、様々な陶磁器がそれぞれの特徴をもって発展してきました。 その中で、みかわち焼は、御用窯として幕府や朝廷への献上品や美術品などを手掛けてきました。 歴史あるみかわち焼の伝統と、手作りの味わいをぜひご堪能ください。 その他肥前やきもの圏の産地 波佐見町 はさみ焼(波佐見焼) 有田町 ありた焼(有田焼) 唐津市 唐津焼 伊万里市 伊万里・鍋島焼 武雄市 武雄焼 嬉野市 肥前吉田焼・志田焼 平戸市 中野焼
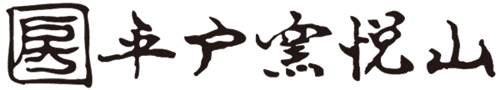
一四代平戸悦山の今村均は技術向上のために伝統的技術を踏襲し、特に「捻り細工技術」は途絶えかけた技術を確立し、発展させた高度な工芸技術と考えられ、2014年 佐世保市指定無形文化財保持者に、2021年 長崎県指定無形文化財保持者に指定されました。自ら図案から轆轤、細工、焼き上げまでの全ての工程を分業はせず、捻り細工技術の最盛期の明治時代にもなかった新たな造形を生み出しています。

郷土玩具 舌出三番叟人形

容貌が色黒で猿に似ていたため「猿の如し」にこころ納まらず、猿を以って三番叟を躍らせ舌を出す人形を作り藩主に献上しました。
首を廻し舌を出す、その面白さに、藩主もとより長崎の出島に滞在していたオランダ人のあいだにも好評を得、大量に輸出されました。
1867年に江戸幕府はフランスの要請でパリ万国博覧会へ参加し、その博覧会での佐賀藩の出品物の中に、平戸三川内藩焼製造の舌出三番叟人形がありました。その人形はナポレオン三世の皇后ウジェニー妃の目に留まり多く買い求められました。
御用窯が廃止になった明治以降も継承され盛んに輸出されました。
現在も一子相伝の昔のままの技法で手作りによって作られています。
 平戸窯悦山の返礼品
平戸窯悦山の返礼品
-
G179p 〈平戸窯悦山〉一四代平戸悦山「菊置きこまつなぎ香炉」

香炉には独楽つなぎや駒つなぎと云われる幾何学模様の吉祥文様を火屋や脚にも連続柄で図案化し彫っています。古くは平安の時代から邪気を払う力があると信じられている菊花を伝統技術の菊細工で飾りました。
容量:菊置きこまつなぎ香炉(直径100㎜*高さ110㎜)\\n共箱(桐箱紐付)
申込:申込時期:通期
配送:決済から20日以内で発送
G181p 〈平戸窯悦山〉菊尽しボンボン入れ

長寿を願う菊花を華やかに蓋に配置した白磁の蓋物です。菊花は伝統技法の菊細工といわれる捻り細工のひとつの技法にて制作、親指先ほどの塊から竹べらを用い、花弁を一枚一枚起こして菊花を彫っていきます。キャンディーボックスや大切なものを入れるための器です。\\n[三川内焼・みかわち焼・うつわ・器・セット・ペア・作家・伝統工芸・肥前・日本遺産]\\n~五感で感じる日本磁器のふるさと~日本遺産・肥前やきもの圏について\\n古くから焼き物の産地として栄えた肥前地区(佐賀県、長崎県)。\\n有名な有田焼や波佐見焼のほかにも、様々な陶磁器がそれぞれの特徴をもって発展してきました。\\nその中で、みかわち焼は、御用窯として幕府や朝廷への献上品や美術品などを手掛けてきました。\\n歴史あるみかわち焼の伝統と、手作りの味わいをぜひご堪能ください。\\n\\nその他肥前やきもの圏の産地\\n波佐見町 はさみ焼(波佐見焼)\\n有田町 ありた焼(有田焼)\\n唐津市 唐津焼\\n伊万里市 伊万里・鍋島焼\\n武雄市 武雄焼\\n嬉野市 肥前吉田焼・志田焼\\n平戸市 中野焼
容量:菊尽しボンボン入れ(直径約105㎜*高さ約85㎜)
申込:申込時期:通期
配送:決済から20日以内で発送
G182p 〈平戸窯悦山〉玩具「舌出し犬」

郷土玩具「舌出三番叟人形」の技でつくられた玩具。胴体も舌も同じ磁土でつくられています。
容量:玩具「舌出し犬」(幅2.2cm*奥行4.7cm*高さ4.5cm)\\n共箱入\\n※サイズは舌の長さを含みません〈15代嗣今村ひとみ作〉
申込:申込時期:通期
配送:決済から20日以内で発送
G183p 〈平戸窯悦山〉郷土玩具「舌出三番叟人形」小

江戸時代からつくられている人形で、藩主もとより貿易のため滞在していたオランダ人の間にも好評で、大量に輸出されました。1867年、パリ万国博覧会にて佐賀藩の出品物の中にあった平戸藩三川内焼製造の舌出三番叟人形がナポレオンⅢ世の皇后ウジェニー妃の目に留まり、多く買い求められました。\\n首を回すことができ、全体を前に傾けると舌が飛び出し、後ろに傾けると舌が口の中に収まります。
容量:郷土玩具「舌出三番叟人形」小(高さ約8cm)\\n共箱入\\n※手作りのため表情、色味、濃淡に個体差があります〈15代嗣今村ひとみ作〉
申込:申込時期:通期
配送:〇2025年4月末~5月上旬予定
G184p 〈平戸窯悦山〉郷土玩具「舌出三番叟人形」中

江戸時代からつくられている人形で、藩主もとより貿易のため滞在していたオランダ人の間にも好評で、大量に輸出されました。1867年、パリ万国博覧会にて佐賀藩の出品物の中にあった平戸藩三川内焼製造の舌出三番叟人形がナポレオンⅢ世の皇后ウジェニー妃の目に留まり、多く買い求められました。\\n首を回すことができ、全体を前に傾けると舌が飛び出し、後ろに傾けると舌が口の中に収まります。
容量:郷土玩具「舌出三番叟人形」中(高さ約10cm)\\n共箱入\\n※手作りのため表情、色味、濃淡に個体差があります〈当代14代今村均作〉
申込:申込時期:通期
配送:決済から20日以内で発送
G185p 〈平戸窯悦山〉郷土玩具「舌出三番叟人形」大

江戸時代からつくられている人形で、藩主もとより貿易のため滞在していたオランダ人の間にも好評で、大量に輸出されました。1867年、パリ万国博覧会にて佐賀藩の出品物の中にあった平戸藩三川内焼製造の舌出三番叟人形がナポレオンⅢ世の皇后ウジェニー妃の目に留まり、多く買い求められました。\\n首を回すことができ、全体を前に傾けると舌が飛び出し、後ろに傾けると舌が口の中に収まります。
容量:郷土玩具「舌出三番叟人形」大(高さ約11cm)\\n共箱入\\n※手作りのため表情、色味、濃淡に個体差があります〈当代14代今村均作〉
申込:申込時期:通期
配送:決済から20日以内で発送
 平戸焼の名でヨーロッパを魅了した長崎デザイン「みかわち焼」
平戸焼の名でヨーロッパを魅了した長崎デザイン「みかわち焼」

みかわち焼の染付は、「一枚の絵のような」と評されることがあります
細やかさと濃淡を駆使した、写実的な絵。
素焼きの白地に、藍色の絵の具・呉須(ごす)を含ませた筆で絵や文様を描き、着色する。手描きでつくられるみかわち焼は、手作りならではの奥深さと温もりがあります。
絵柄の輪郭(りんかく)を描いて着色していく作業「骨描(こつが)き」のあとに、呉須を面として染る「濃(だ)み」でひとつの絵柄を作り上げていく。職人の技によりみかわち焼はつくられています。

やきものに描かれる絵は、陶工たちが器に同じ絵柄を何度も繰り返し描くうちに自然と省略や変形が起こり、パターン化された「文様」として定着していくものです。しかし、みかわち焼は、そのような図案の変形を経ることはなく、いまでも絵画を描くように、一筆ひとふでを運んでいきます。そのため、やきものの絵付けとしては珍しく、濃みの濃淡で立体感や遠近感を表現するなど、絵画的な手法が大切にされ続けています。